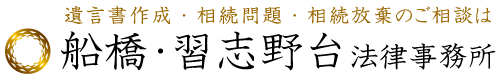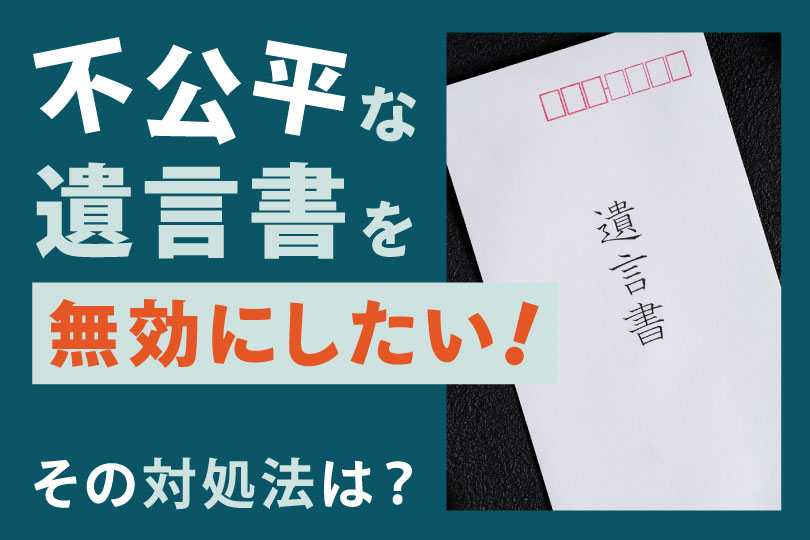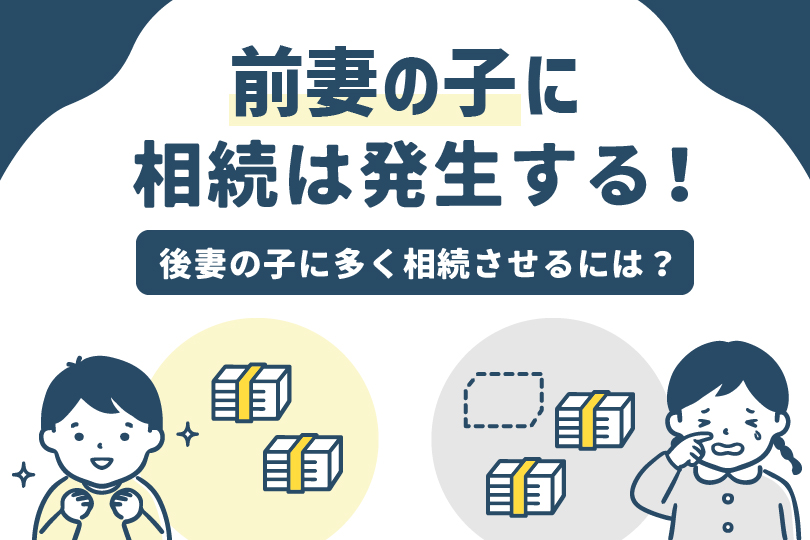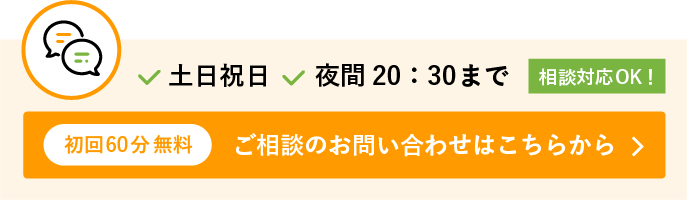コラム
終活で役立つ遺言と死後事務委任契約
2022.12.23
終活で役立つ遺言と死後事務委任契約

船橋習志野台法律事務所の弁護士の中村です。この10年ほど「終活」という言葉が流行っています。
終活とは自らの死亡後のこと、すなわち葬儀、遺産分割、各種契約の解約、名義変更、遺産の寄付・使い道など多様な事務処理について、生前判断能力が低下する前に、明示的な意思表示をして準備をしておくことです。
終活の典型が「遺言」になります。遺言は法的効力があり、遺産の分配等を取り決めることができます。しかし、各相続人に具体的な指示をすることはできず、その穴を埋めるのが死後事務委任契約です。本コラムでは、終活の重要な手段である遺言と死後事務委任契約について解説します。
目次
遺言は遺産の使い道とそれに付随する事項を遺言者1人の意思で決められる

遺産の分配は基本的には遺言通りになる
遺言書の作成により、残された親族にどのように遺産を分配するか決めることができます。
極端な分配をして、1人を0にするなどのような遺言書であれば、死後、遺留分の請求をされる余地があるものの、おおむね、自己の意思どおりに遺産の分配方法を決めることができます。
また、NPO法人などの第三者へ寄付することもできます。
遺言で条件を付けることもできる
また、遺産の取得に条件をつけることができます。典型例は、子どもに多くの財産を取得させる代わりに、残された配偶者(子にとっての親)の世話をすることを条件とするものです。少し変わった例ではペットの飼育を条件に一定額の遺産を取得させるという遺言書もあり得ます。
ただ、残された親の判断能力が低下していると遺産を取得した子どもが約束に反して親の世話をしなかったとしてもこれを追及できる人がいません。ペットは自分から話せないのでなおさらです。
信託制度で条件付き遺言の目的を達成する
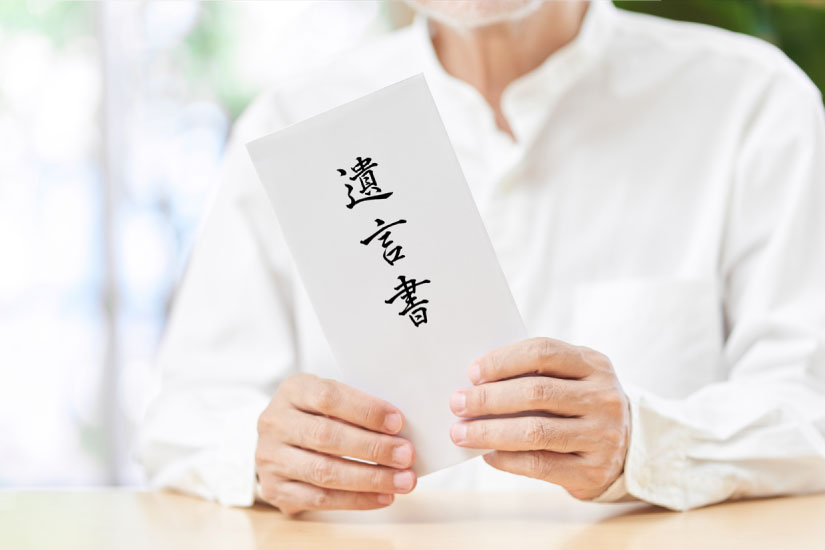
そこで、このような条件付き遺言の目的を達成するため、信託という制度を用いることができます。具体的には、遺言の効力が発生した時点で遺産のうちの一定額を第三者に預けます。これを信託という預かって遺産を管理する人を受託者といいます。
そして、遺産を取得する人に定期的に預かっている遺産を少しずつ支給して、残された親なりペットの世話を怠ったら支給を止めることができます。このような形で残された人の世話を担保することができます。
相続人の行為を制約することはできない
遺言でできないことは、端的にいうと残された遺族(相続人)の行為を制約することです。
例えば、遺言者の自宅が先祖代々の土地なので、長男に取得させたうえ将来にわたって売却をしないでほしいと遺言書に記載をしても効力がありません。
また、先祖代々の土地なので、長男の次に相続するのは長男の長男(孫)にして欲しいと遺言書に記載をしても効力がありません。その他、葬儀の費用だったり、携帯電話、自動車、NHKなど諸々の名義変更について個別に指示を出す遺言も効力がありません。
死後事務委任契約について

このように、遺言は財産の分配方法を決めることができますが、各相続人に何等かの具体的な行為をお願いすることはできません。その穴を埋めるのが死後事務委任契約になります。
死後委任事務契約は、被相続人(遺言者)の生前のうちに信頼できる人に死後の事務処理について個別具体的に委任する契約です。
通常の委任契約は、委任者(事務処理を頼む人)が死亡すると終了することになりますが、死後委任事務契約は、委任者の死亡後の事務を依頼することが前提なので、死亡後にも契約の効力が維持されます。
死後委任事務契約では、
- 知人・勤務先等への死亡の通知
- 遺体引き取り、死亡届、火葬、納骨など
- 病院の退院手続き、医療費清算
- 部屋の明け渡し
- 家財道具処分、施設利用料などの清算
- 公共料金、SNS,各種契約の解約
- PC・スマートフォン上のデジタルデータの消去
- ペットの里親探
- 年金、介護保険の手続き
- 税金の清算
通常、これらの事務手続きは、死後委任事務処理契約がなければ、残された相続人が担うことが多いです。ただ、子どもがおらず他の親族も遠方であまり交流がなければ、上記のような細かい事務をこなすことができません。
そのため生前のうちから、信頼できる人と十分に打合せをして死後の事務処理に必要な情報を提供したうえで、死後に備えるのが死後事務委任契約です。
子どものいない家族に適した契約といえます。仮に、子どもがいても疎遠になっていて、近くにいる第三者と死後事務委任契約を締結すると、相続人から委任者の地位を承継したと主張して死後事務委任契約の解除を主張することが考えられます。
死後事務委任契約の締結の際にはこのような解除権を制限する条項を設けておくのがよいでしょう。
トラブルを回避するには専門職の利用がおすすめ
遺言書と死後事務委任契約を活用することで、終活において自らの意思を死後に反映させつつ、残された人同士の紛争や混乱をある程度回避することができます。
ただ、死後事務委任契約は、亡くなる人が契約の当事者になるという特殊な契約類型であり、十分に専門家の相談が必要です。弁護士へ相談してその内容を十分に精査することが必要です。