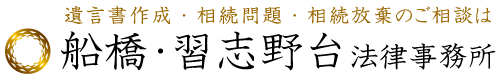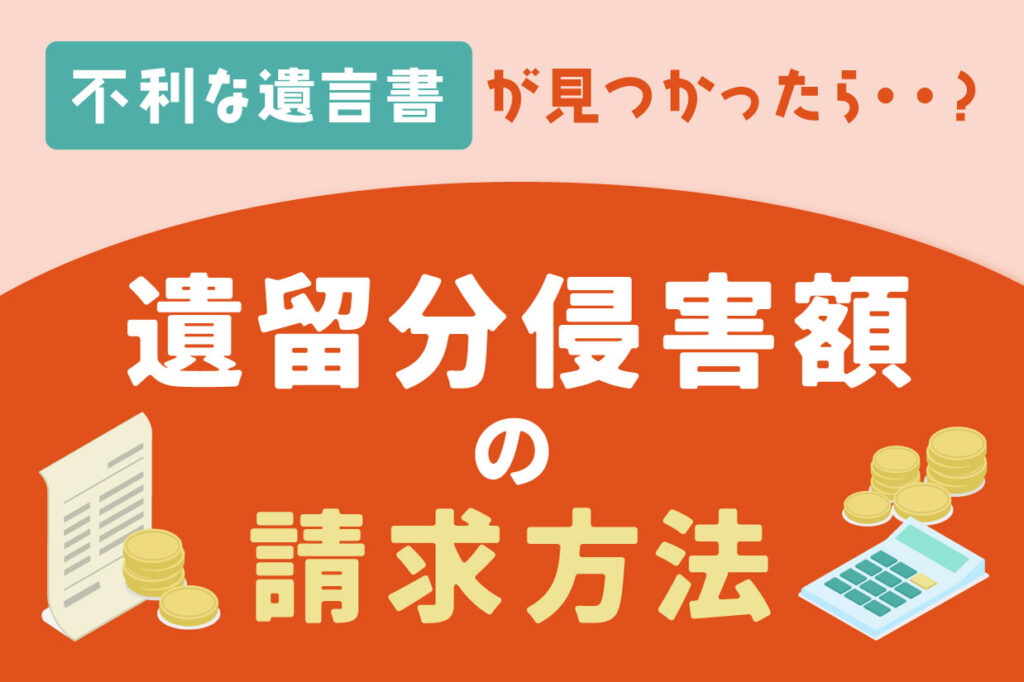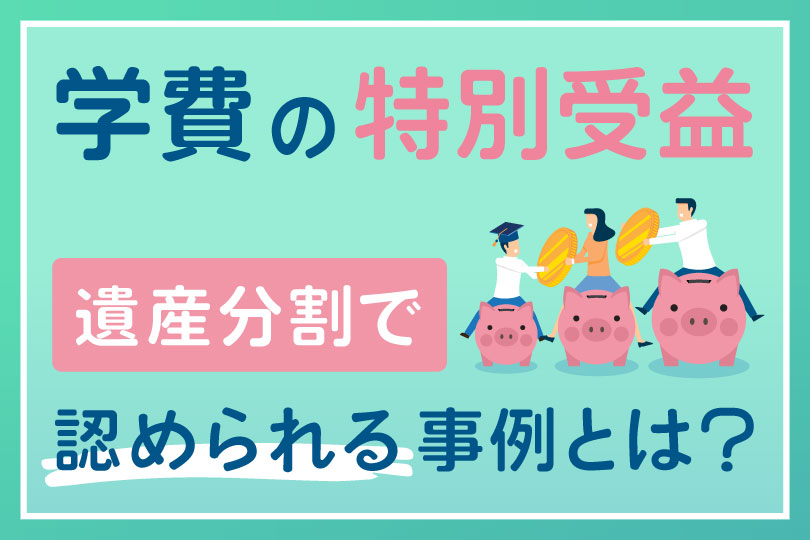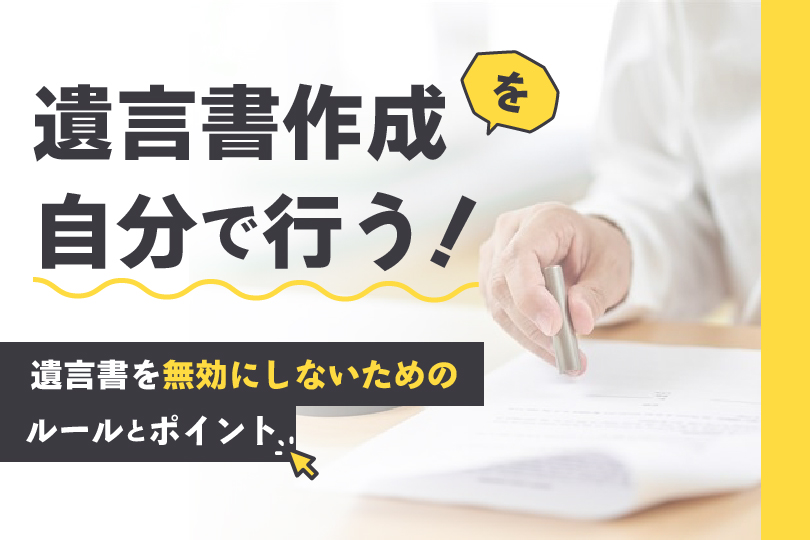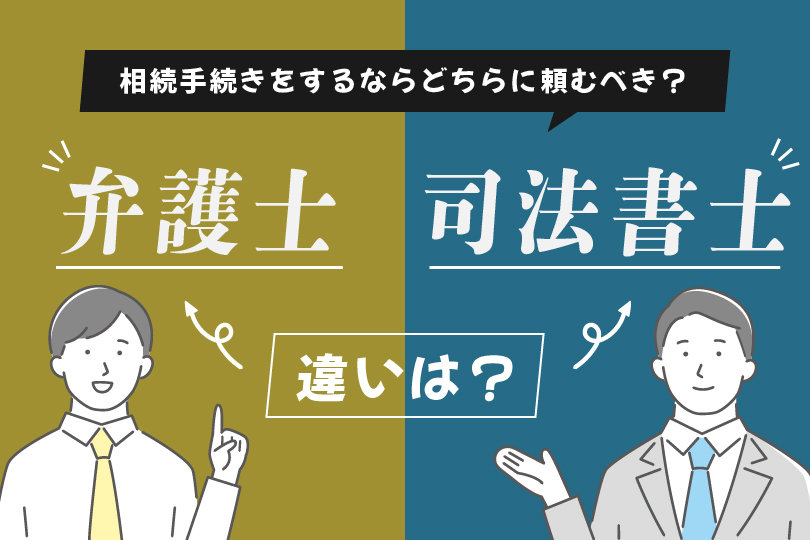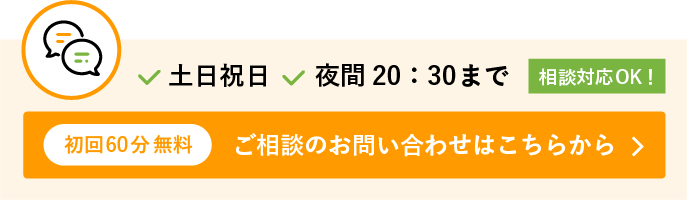コラム
前妻の子に相続は発生する!前妻の子への相続を少なくする方法とは
2022.12.26
前妻の子に相続は発生する!前妻の子への相続を少なくする方法とは
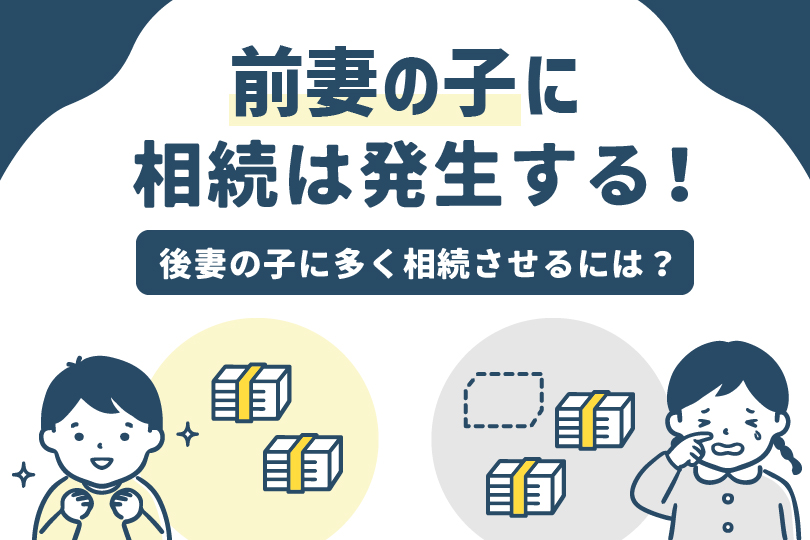
こんにちは。船橋・習志野台法律事務所です。
夫に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合、前妻の子にも相続が発生するのはご存知でしょうか?
前妻の子と何年も会ってないのになぜ?と思う人もいると思いますが、法律上は親子関係が成立しているため、前妻の子にも相続権が認められます。
現在の妻との間に子どもがいる場合はできるだけ今の妻とその子どもに相続させたいと思う人も多いと思いますが、トラブルに発展するケースも多くとてもシビアな問題です。
今回は前妻の子の相続について、前妻の子への相続分を少なくし後妻の子に多く残すための方法についてご紹介していきます。
目次
前妻の子にも相続する権利がある

前妻の子と後妻の子の法定相続分は同じ
離婚した妻との間に子どもがいる場合、その子どもに相続権は発生します。まずはその子どもにどれだけ遺産を分配しなくてはいけないのか確認しましょう。
法定相続人(相続人となる人)は配偶者と血族です。配偶者は必ず相続人となり、血族は優先順位が決まっています。
- 第1順位:子および代襲相続人※1
- 第2順位:両親などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹および代襲相続人
※1 代襲相続とは法定相続人である子ども(または兄弟姉妹)が死亡している場合、代わりに孫(または甥・姪)が相続することができる
これらを踏まえた上で、例えば、前妻との間に子どもが2人、今の妻との間に子どもが1人いたとしましょう。
夫が亡くなった場合、法定相続人は配偶者と子どもです。子どもは前妻・後妻どちらの子どもも含まれ、そこに優劣はありません。
民法が定める法定相続分は「配偶者が2分の1、子どもが2分の1」です。同じ順位の人は複数いる場合、相続は均等に分けられるため、子ひとりに対して法定相続分は6分の1となります。
前妻に相続権はない
反対に、配偶者に関しては離婚をした時点で法的に相続関係は解消されます。
よって、再婚後相続権を持っているのは後妻のみとなり、前妻は相続権がないため遺留分なども請求することができません。
しかし、前妻の子どもがまだ未成年の場合、前妻が子供の法定代理人となるため遺産分割協議への参加や遺産の管理も前妻が行うことになります。トラブルに繋がらないように注意が必要です。
前妻の子への相続を少なくする方法

ここで多くの人が考えることが「前妻の子に相続させたくない」といことです。結論から言うと前妻の子に相続させないことはできません。
何も対策をしない限り前妻の子にも後妻の子と同じ額の相続が発生することになります。
一切相続させないのであれば、「遺産を一切残さない」ことが必要です。しかし、現実的には難しく配偶者や後妻の子も遺産を相続できなくなるので、ここからはなるべく前妻の子への相続分を少なくする方法を紹介いたします。
遺言書に希望の相続内容を書く
できるだけ相続を希望通り実現したいのであれば遺言書の作成がおすすめです。
例えば、「現在の妻と子どもにすべての遺産を相続させる」という趣旨の内容で遺言書を残せば、それに沿って遺産相続がすすめられます。
遺産分割協議をする必要もないため、前妻の子の連絡する必要はありません。
ただし、前妻の子には遺留分(相続人が取得できる最低限の取り分)が存在するため、もし前妻の子が遺留分を請求してきた場合は財産を分割する必要がでてきます。
トラブルをなるべく避けるという点では、前妻の子の遺留分を配慮した遺言書を作成するとよいでしょう。
生前贈与をする
生前に今の妻とその子どもに生前贈与すれば、前妻の子へ相続する財産を減らせると考える方もいるでしょう。
しかし、生前贈与は特別受益※2にあたり、遺産分割の際に相続財産として戻して計算することになります。
※2 特別受益は複数の相続人がいる場合、一部の相続人だけが被相続人から受け取った利益のこと。生前贈与・遺贈・死因遺贈がそれにあたり、これらは相続財産を公平にわけるため、遺産相続の際は戻して計算します。
そのため、後妻の子に多く財産を相続させるために生前贈与をすることはあまり意味がないのでおすすめはできません。
自分名義の財産を減らす
前妻の子に相続されるのは、実の親の名義の財産のみです。
そのため、後妻や後妻の子のために遺しておきたい財産は自分名義ではなく、後妻名義にして遺しておくと良いでしょう。
生命保険を掛ける
現金で遺産として残すのではなく、生命保険を掛けるという方法があります。
現金と違って、遺産分割協議の対象とならないこと、また原則として遺留分の対象にもならないことがメリットです。後妻の子を受取人にしておけば、遺産分割とは関係のないところで受取人が全額を受け取ることができます。
前妻の子とトラブルを避ける方法

前妻の子や前妻との間に相続をめぐってトラブルが起きないためにどのような点に注意していけばよいのかを見ていきましょう。
遺産分割協議の通知を行う
離婚歴のある夫が死亡し、遺言書を残していない場合、相続手続きをするには遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は法定相続人全員が参加しないといけません。
例えば、前妻の子を抜きに遺産分割協議をした場合、それはなんの意味も持ちません。必ず前妻の子にも通知をし、遺産分割協議書に署名押印をしてもらう必要があります。
法定相続人である前妻の子が参加していない遺産分割協議は無効となります。後出しで通知を行うとトラブルになりやすいので必ず事前に通知をするようにしましょう。
遺留分の対策を行う
遺言などで「遺産は全て後妻の子に」と書かれていたとしても、前妻の子には遺留分を請求する権利があります。前妻の子は本来の法定相続分の2分の1に相当する金額の請求が可能です。
そのため、最初から遺留分が請求されることも考慮して、慌てないように事前に準備をしておきましょう。
以下のような備えをすることができます。
- 遺言で前妻の子にも最低限の遺産を相続することを明記する
- 遺留分を申請された時にすぐに渡せるように現金を用意しておく
遺留分や前妻の子の相続分にも配慮した遺言を作成するには、専門家のサポートが必要です。ぜひ弁護士に相談しトラブルを避ける対策をしてみてください。
まとめ
今回は前妻の子の相続についてまとめました。
- 前妻の子にも相続権は発生し、後妻の子と均等に相続する必要がある
- 前妻の子だけ相続させないはできない
- 遺言書を作成することで希望の相続が実現できる可能性がある※遺留分を考慮すると良い
弁護士は遺産分割協議の代理人として交渉をすることができます。「前妻の子とやりとりをしたくない」という人は弁護士を通せば直接やりとりしなくても、遺産分割協議をすすめられます。
また「前妻の子の居場所がわからない」というケースもあるでしょう。そういった場合、弁護士に相談すれば調べて通知することができますよ。
前妻の子がからむ相続のやりとりは面倒なことも多いです。不安なこと・お困りことがあればぜひお近くの弁護士にご相談ください。
関連記事