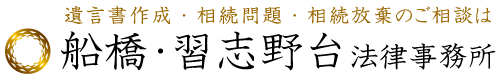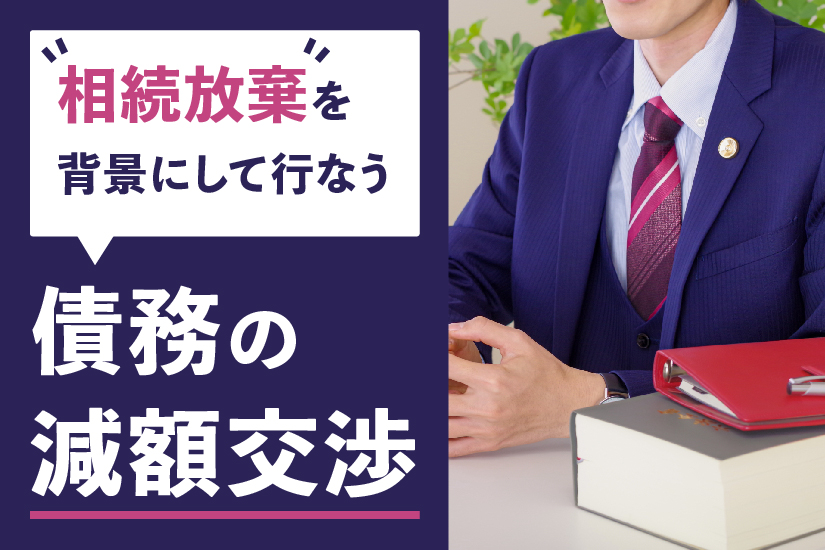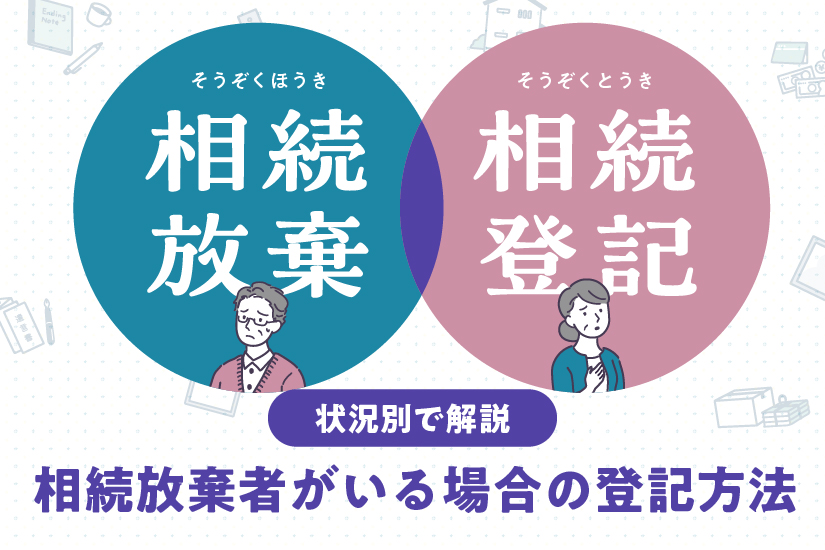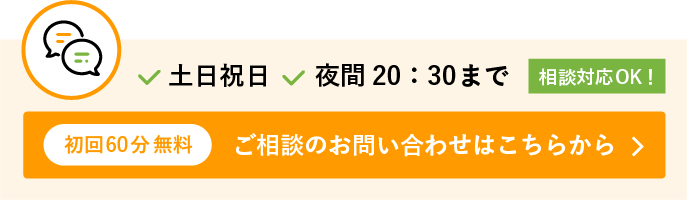コラム
生活保護受給者が相続放棄をしたい場合の手続き方法とは?相続の基礎と注意点も解説
2024.05.10
生活保護受給者が相続放棄をしたい場合の手続き方法とは?相続の基礎と注意点も解説

「生活保護を受給しているけれど、相続放棄は可能なの?」「相続放棄をしたいが、どんな手続きが必要なの?」などと悩んでいませんか?
生活保護受給者が相続人になった場合、相続放棄は原則できませんが、生活が困窮する場合は相続放棄が可能なケースもあります。相続放棄を実施するかどうかは状況によって異なるため、該当するかどうか把握しておくことが大切です。
本記事では、生活保護受給者が相続放棄を考慮すべき状況を解説しています。生活保護受給者が相続放棄をしたい場合の手続き方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
生活保護受給者でも相続放棄は可能?
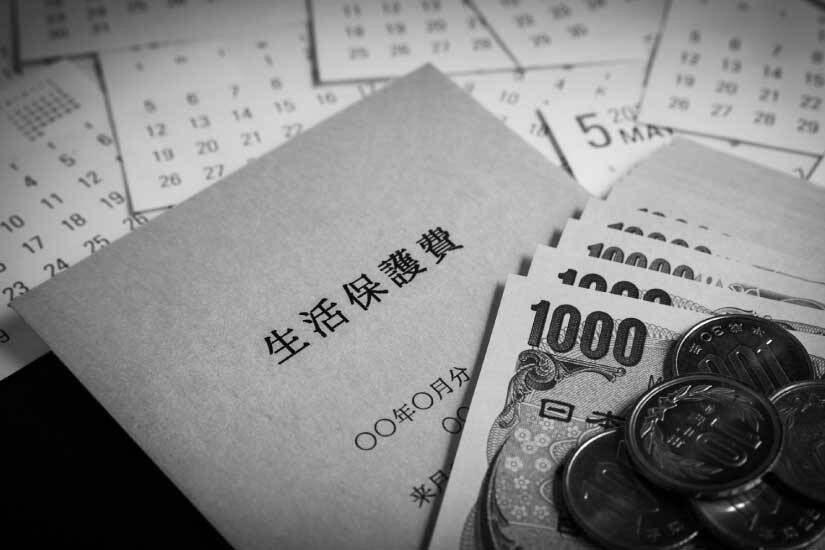
生活保護受給者が相続人になった場合、相続放棄は原則できません。ただし、相続する財産の中で借金や負債が多く、相続によって生活が困窮する恐れがある場合、相続放棄が可能なケースが存在します。
ただし、生活保護受給者の場合、相続によって得られる財産が生活保護の受給資格に影響を及ぼす可能性があります。
相続放棄を検討する際には、相続される財産が生活保護受給者の経済状況にどのような影響を与えるか、慎重に評価することが重要です。
生活保護受給者が相続放棄を考慮すべき状況
生活保護受給者が相続放棄を実施するかどうかは、状況によって異なります。以下の状況にあてはまる場合、相続放棄を検討しましょう。
- 相続財産よりも負債の方が大きい場合
- 相続財産を受け取ることによる生活保護費の減額が懸念される場合
- 相続財産が処分困難な場合
それぞれ詳しく解説します。
相続財産よりも負債の方が大きい場合
相続財産よりも負債の方が大きい場合、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をしなければ、負債を相続することになり、生活保護費が減額されたり、最悪の場合、生活保護を受けられなくなる可能性があります。
相続財産を受け取ることによる生活保護費の減額が懸念される場合
相続財産を受け取ると、生活保護費が減額される可能性があります。
生活保護費の減額幅は、相続財産の額や生活保護受給者の状況によって異なりますが、場合によっては生活保護が停止・廃止されるケースもあります。
相続財産が処分困難な場合
相続財産が不動産や山林など、処分が困難な場合も、相続放棄を検討する必要があります。処分困難な財産を相続すると、維持管理費などの負担が生じ、結果として負債を相続してしまうことになる可能性があります。
生活保護受給者が相続放棄をしたい場合の手続き方法
生活保護受給者が相続放棄を行う場合、手続きが必要です。具体的な手続き方法をまとめると以下の通りです。
- 福祉事務所に相談・届出を行う
- 他の相続人との遺産分割協議を実施する
- 相続財産の名義変更を行う
それぞれ詳しく解説します。
福祉事務所に相談・届出を行う
相続放棄の手続きを始める前に、まず福祉事務所に相談しましょう。福祉事務所では、生活保護受給者の状況を考慮した上で、相続放棄に関する具体的なアドバイスや指導を受けることが可能です。
専門家のアドバイスを受け、手続きの進め方や必要な書類を理解してから届出を行いましょう。
他の相続人との遺産分割協議を実施する
相続放棄を検討している場合でも、他の相続人との遺産分割協議が必要になる場合があります。相続放棄の意向を他の相続人に伝え、相続財産に関する分配をどうするかを決めるためにも、話し合いは重要です。
遺産分割協議を通じて話し合いが進めば、相続放棄の意向が正式に記録されます。相続放棄の意向を記録として残しておけば、財産分配に関するトラブルも避けられます。
相続財産の名義変更を行う
相続放棄が正式に認められた後、相続財産の名義変更を行う必要があります。不動産登記簿や銀行口座など、相続によって受け継がれる財産の法的な所有者を更新する手続きです。
相続放棄によって、受給者は相続財産を受け取らない選択をしたため、名義変更のプロセスでは、相続財産が他の相続人に移転されます。名義変更を適切に行うことで、相続放棄の結果としての法的な責任から解放されます。
生活保護受給者が相続放棄する際の注意点

生活保護受給者が相続放棄する場合、以下の点に注意しましょう。
- 相続放棄の期限は3ヶ月以内
- 少額の遺産であれば生活保護の受給を続けられる
- 相続放棄の手続きは複雑
それぞれ詳しく解説します。
相続放棄の期限は3ヶ月以内
相続放棄を行う場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行いましょう。期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなります。
期間内に必要な書類を集め、手続きを進めるためにも早めに行動が必要です。相続放棄の申立は法的な手続きであるため、書類の準備や提出方法に誤りがないよう注意しましょう。
少額の遺産であれば生活保護の受給を続けられる
相続する遺産が少額である場合、相続放棄をせずとも生活保護の受給を続けられる可能性が高いです。相続によって得られる遺産が生活保護の基準額を超えない場合は、受給資格に影響を与えません。
ただし、どの程度の額であれば影響がないのか判断は難しいため、相続放棄すべきか迷ったら専門家に相談しましょう。
相続放棄の手続きは複雑
相続放棄の手続きは複雑です。家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする前に相続人全員の同意を得たり、相続財産の詳細な調査を行う必要もあります。
また、相続放棄の申立には正確な書類の準備と提出が必要です。手続きをスムーズに進めるためには、相続関連の法律に詳しい専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
相続放棄が不安な場合は専門家に相談しよう
生活保護受給者が相続人になった場合、相続放棄は原則できませんが、生活が困窮する場合は相続放棄が可能なケースもあります。借金や負債などのマイナスの財産を相続したり、相続人が生活保護を受給している場合は相続放棄を検討しましょう。
ただし、相続放棄の手続きは複雑なため専門家のアドバイスのもと進めるのが得策です。もし相続放棄についてお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。
船橋・習志野台法律事務所は、土日祝日も対応・相続放棄の手続きはメールで完結させることが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。