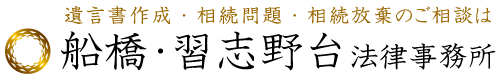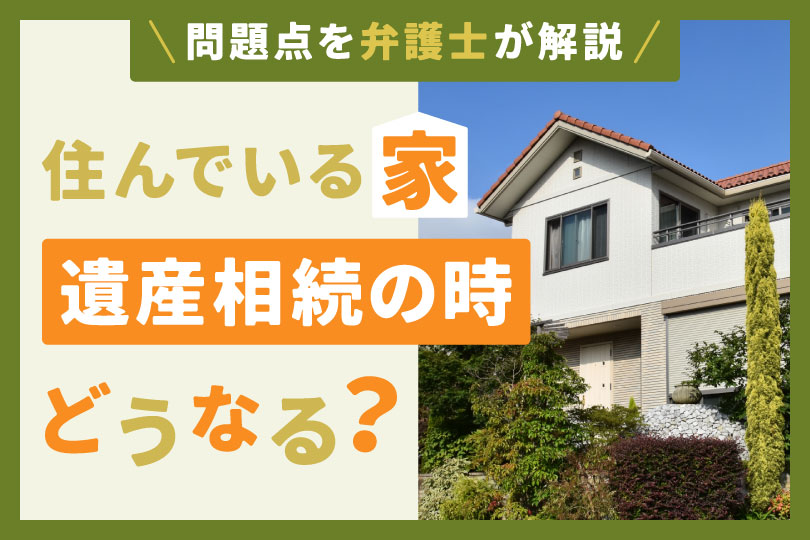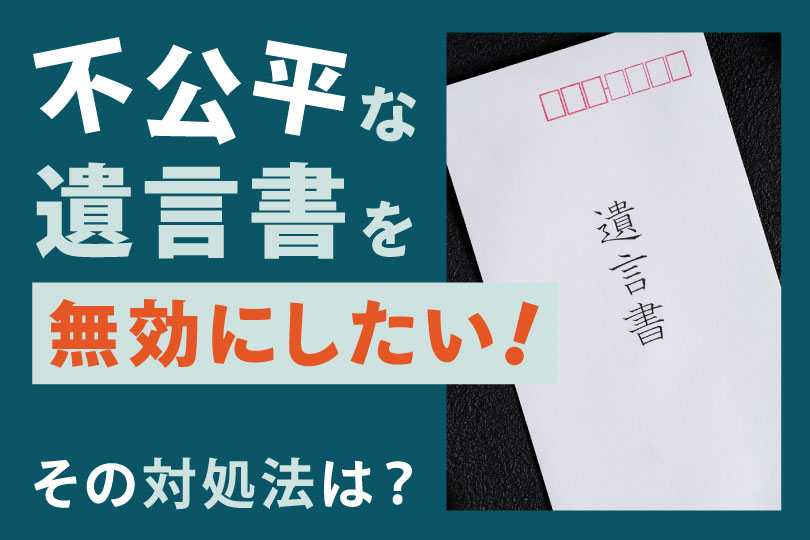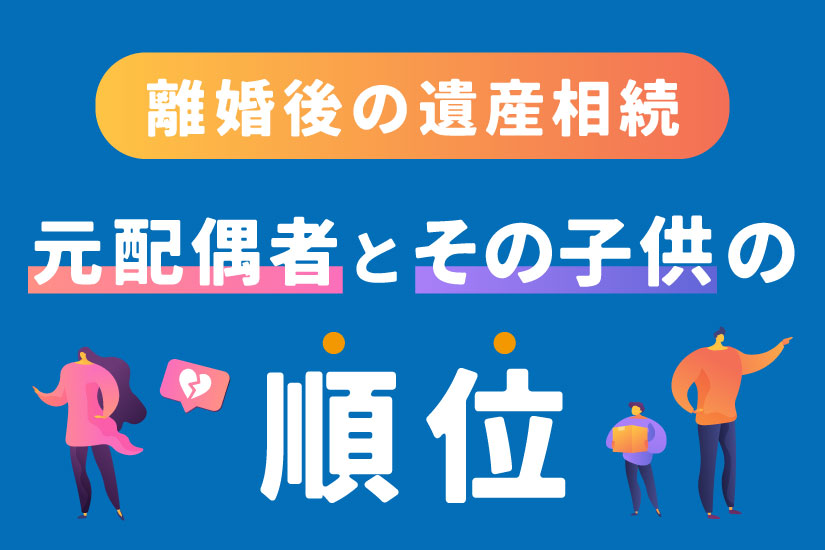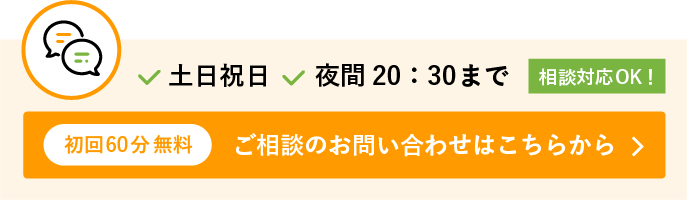コラム
被相続人の口座が凍結!法定相続人が預金が下ろせなくなったときの対処法
2023.01.13
被相続人の口座が凍結!法定相続人が預金が下ろせなくなったときの対処法
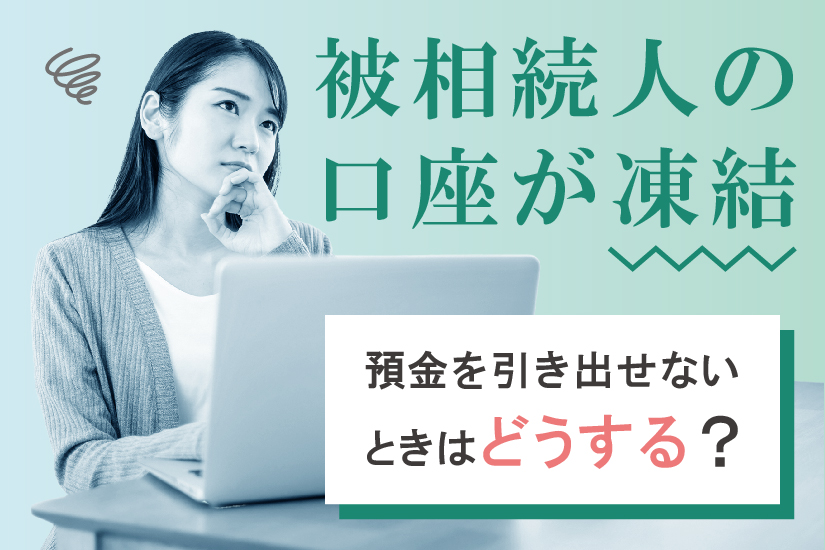
相続人が被相続人の死後、預金口座から預金を引き出そうとしても貯金口座が凍結されていることがあります。葬儀費用の支払いなどをするために預金を引き出したいのに、それができないとなれば非常に困った事態です。
今回はそういったケースが心配な人のために預金口座の凍結される状況の説明から、口座凍結を解除する3つのステップ、口座凍結を解除しない方がいいケースを解説します。
目次
亡くなった人の預金口座は凍結される
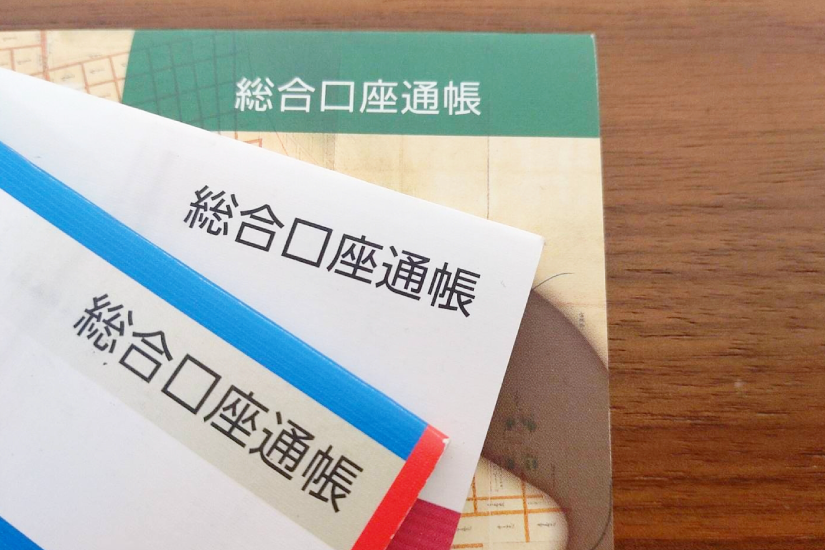
口座名義人の訃報を銀行が知ると口座は凍結される
銀行に預金口座を持っている人が病気や事故で亡くなった際、銀行がその事実を知れば預金口座の凍結を行います。
その理由は、預金も家や債権と同じく相続財産に含まれるためです。必要だからと一部の相続人が預金を引き出してしまうと、遺産分割をするときに他の相続人の取り分が減って権利が侵害される恐れがあります。
例えば、故人に2人の相続人がおり、1000万円の預金があった場合。
2人の相続人のうち1人が勝手に100万円を引き出せば、もう1人の相続分は450万円です。本来ならば、500万円の相続だったことを考えると、50万円は取り分が減ることになります。
何らかの形で銀行が口座名義人の訃報を知ったならば、機先を制して預金口座の凍結をすることで相続人であろうとも勝手に預金を引き出す事はできなくなります。
口座が凍結された状態であれば、相続財産を確定でき公平に遺産分割ができます。預金を引き出したい相続人にとって口座の凍結は不便を感じるでしょうが、預金の引き出しに伴う相続トラブルを防止するには効果的です。
凍結された預金口座から引き落としによる支払いはできなくなる
銀行が亡くなった人の預金口座を凍結すれば、法定相続人であってもATMや窓口から預金を引き出せなくなるだけでなく、引き落としによる支払いもできなくなります。
亡くなった人が世帯主であれば、公共料金等の支払いで口座引き落としを設定している場合や、生前に行った買い物など支払いもできなくなるでしょう。残された相続人たちにとっては困った事態です。
次の段落では口座凍結を解除する方法についてご説明いたします。
口座凍結を解除する3つのステップ

相続人の1人が銀行に凍結解除の依頼をする
亡くなった人、法的に言えば被相続人の名義となっている預金口座が凍結された場合、口座の凍結を解除する方法もあります。それは、相続人の1人が解除を銀行に求めることです。
2019年に施行された改正民法に基づく仮払い制度では、相続人が葬儀代代金や生活費の支払いができるよう、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、上限150万円まで引き出せるようになります。
しかしながら、相続人が何の準備もなしに銀行へ赴き、凍結解除をして欲しいと言っても手続きをしてくれません。必要な書類を揃えて、提出したときに預金口座の凍結が解除されます。
必要書類を揃えるため、役所から郵送で取り寄せるとなれば、輸送に日数がかかります。速やかに預金口座の凍結解除をして欲しいならば、事前に手続きに必要となる書類を知っておくとスムーズです。
手続きに必要な書類を準備する
口座凍結を銀行に求める時、凍結解除に必要となる書類を準備します。この必要書類ですが、遺言書の有無で提出しなければいけないものが変わる場合や、必要書類が多岐にわたるため完璧に揃えるのは容易なことではありません。
相続問題を専門とする弁護士に相談しておけば、書類のチェックや銀行との交渉などを依頼できるため安心です。親族の死は精神的にも大きな負担となるため、無理をせずに弁護士に相談することをおすすめします。
遺言書がある場合
遺言書があった場合に準備しておく書類は以下のとおりです。
- 被相続人名義の預金口座の通帳、キャッシュカード
- 遺言書
- 自筆証書遺言だったときに必要となる検認調書または検認済証明書
- 被相続人の戸籍謄本または出生から死亡までの連続した記録となる全部事項証明書
- 預金を相続する相続人の印鑑証明書、遺言執行者が専任されている場合は遺言執行者の印鑑証明書
この中で、検認調書または検認済証明書は、家庭裁判所に遺言の検認をしてもらうことで入手できる書類です。家庭裁判所へ検認の申立をするためには、申立書に加えて遺言者や相続人の戸籍謄本などを準備しなければいけません。
遺言執行者の選任審判書謄本も、遺言執行者選任の申立を家庭裁判所に行わなければいけないので手間がかかります。
遺言書がない場合
遺言書がない場合に、準備しておく書類は以下のとおりです。
- 被相続人名義の預金口座の通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議が済んでいる場合は遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、全部事項説明書のいずれか
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
戸籍謄本または全部事項証明書と印鑑証明書は、相続人全員のものが求められます。一部の相続人だけでなく、全員で凍結解除の申立ができるように話し合いが必要です。
遺産分割協議で意見の対立もあるでしょうが、預金を引き出して葬儀代金の支払いなどができるように被相続人間で協力できる点では協力して支払いを行ったほうが良いでしょう。
準備した書類を銀行に提出する
必要な書類を全て揃えたら、銀行へ提出します。不備がなければ提出から10日程度で解除の手続きは完了します。預金を引き出せたら、必要な支払いをしていきます。
今後も続く引き落としなどは、いつまでも被相続人の預金口座からの引き落としにしておかず、相続人の預金口座からの引き落せるように設定を変更しておきましょう。
口座凍結を解除しないほうがいいケース

マイナスの財産が多く相続放棄をする可能性があるケース
相続が発生するとしても、残されたのがプラスの財産とは限りません。消費者金融からの借り入れや住宅ローンの残債など、マイナスの財産という可能性もあります。
そういった場合は、返済義務を免れる方法として相続放棄が検討されます。相続放棄は、プラスの財産だけを相続してマイナスの財産を相続放棄するということはできません。
もし預金に手をつけていれば、相続の単純承認(無条件でプラス・マイナスの全財産が相続されること)が行われたとみなされて、相続放棄ができなくなります。
事前にマイナスの財産があるとわかっているならば、預金口座は凍結されたままにしておきましょう。
口座の残高が少ないケース
預金口座の凍結解除には、用意するべき書類が多く時間もかかります。口座に入っている預金が100円、1,000円などの少額であれば、労力と費用と釣り合いません。
下手に凍結解除の手続きをせず、そのまま放置しておく方が賢明です。なお放置した場合、預金債権は10年が経過すると時効で権利が消滅する恐れがあります。
預金口座の凍結解除をしないつもりであれば、あらかじめ預金再建の時効について理解しておかなければいけません。
被相続人の預金口座が凍結されることを想定して遺言書を作成しておこう
被相続人の預金口座は、銀行が訃報を知ると凍結される恐れがあります。必要書類を提出すれば凍結解除が可能ですが、凍結解除の手続きも簡単ではありません。
遺言書がない場合は、手続きが更に複雑となるます。被相続人が、生前に預金口座を整理したり遺言書を作成しておき「誰が何を相続するのか」をきちんと明記すると手続きをスムーズに行えます。
遺言書を作成する際は、相続発生後のトラブルを防ぐためにも弁護士への相談をおすすめします。