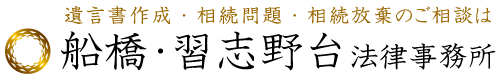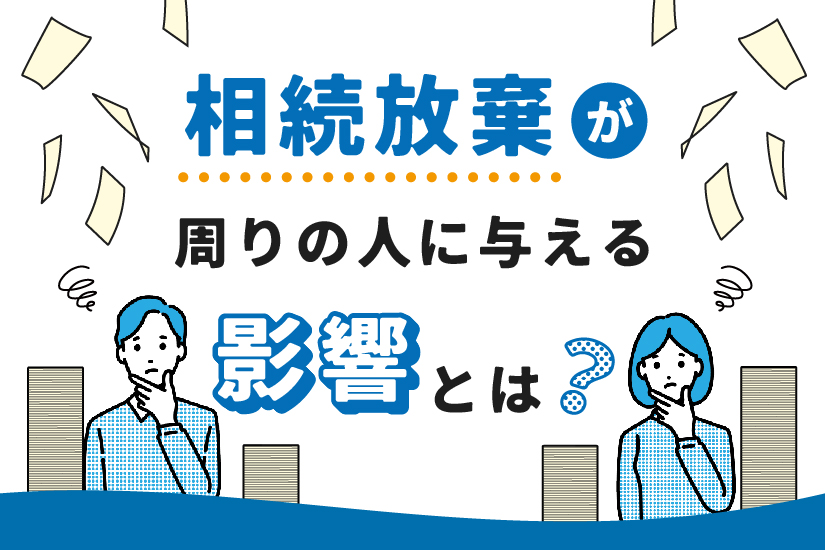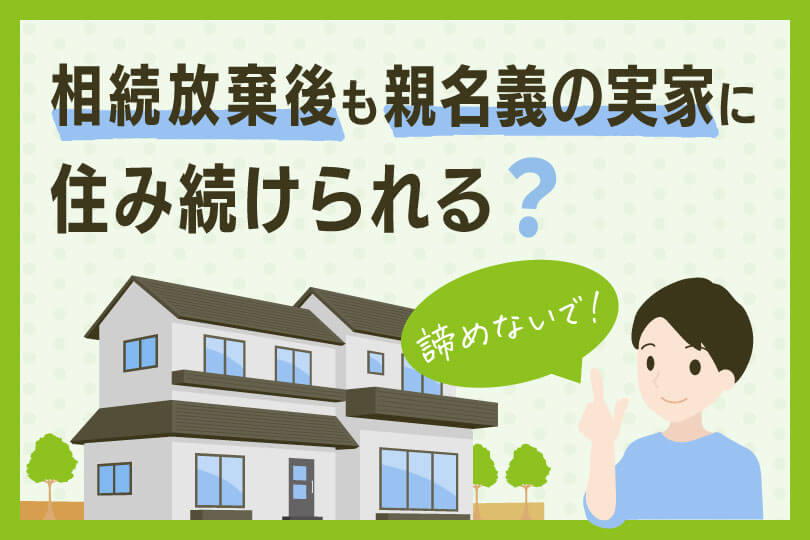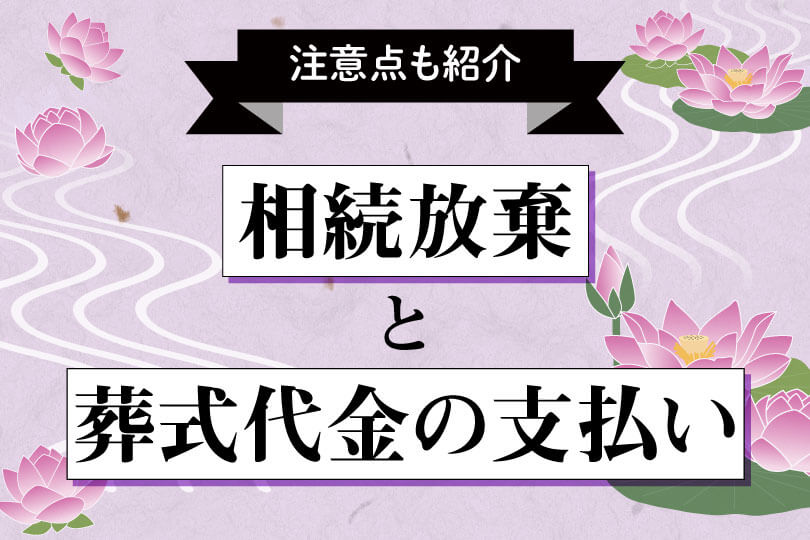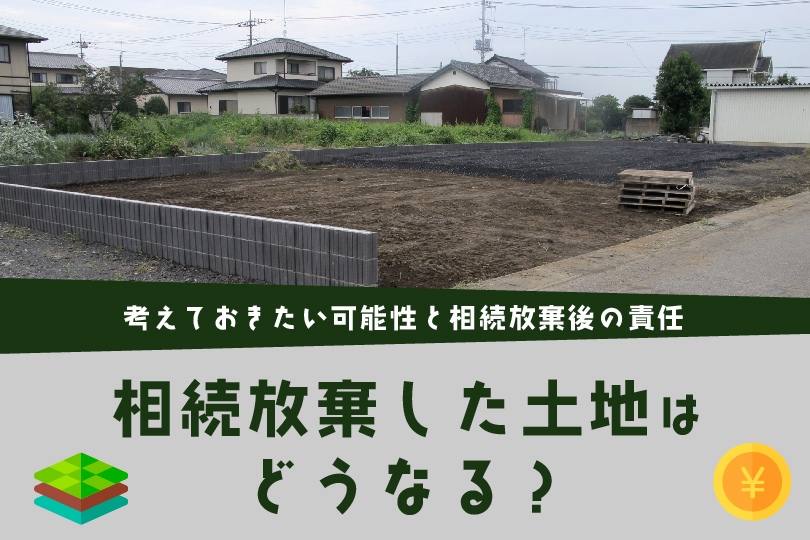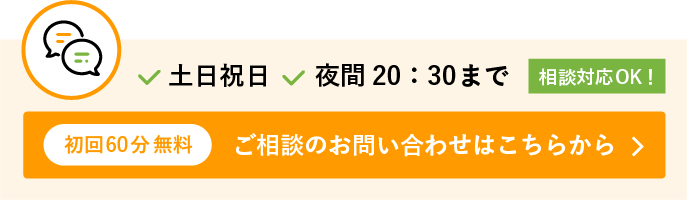コラム
相続放棄の手続きに必要な書類と申請の流れとは?相続人の立場別で紹介
2024.06.25
相続放棄の手続きに必要な書類と申請の流れとは?相続人の立場別で紹介

相続放棄の手続きには、相続放棄申述書や被相続人の住民票除票、または戸籍附票といった書類が必要です。
相続人の立場によって必要書類は異なるため、手続き方法だけでなく用意すべき書類の内容を把握しておくことが大切です。
本記事では、相続放棄の手続きの基本や必要書類、具体的な申請の流れを解説します。相続放棄の手続きにおける注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄の手続きの基本
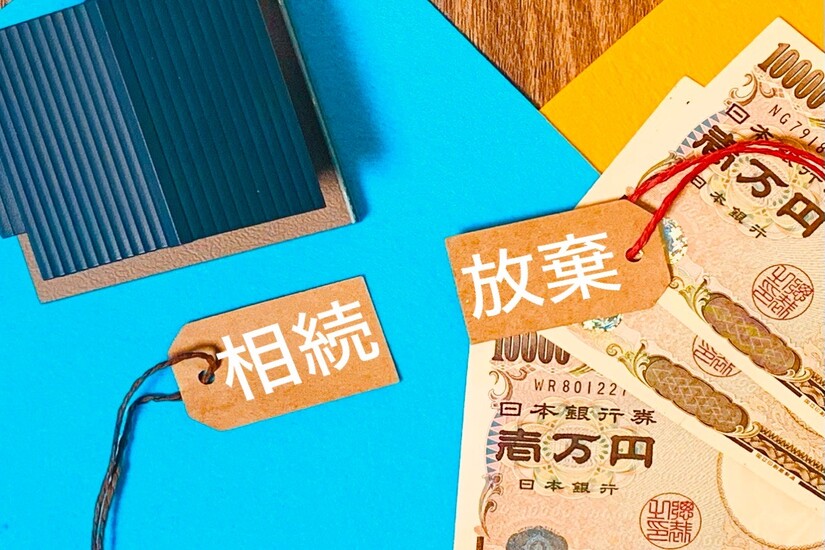
相続放棄とは、被相続人から引き継がれる財産を法的に放棄する手続きです。手続きを正しく行えば、被相続人の財産を受け取る権利と債務を引き継ぐ義務の両方を放棄します。
財産だけでなく負債の相続も発生しないため、借金返済の義務を負う必要もなくなります。
相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われ、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを完了しなければなりません。
相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の手続き時には提出すべき書類がありますが、相続人の立場によって必要書類が異なります。相続人の立場別で必要書類をまとめると、以下の通りです。
相続人全員の場合
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
(※相続放棄する本人と同じ名義なら不要)
- 収入印紙(800円分)
- 切手
配偶者・子の場合
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
(※相続放棄する本人と同じ名義なら不要)
- 収入印紙(800円分)
- 切手
孫の場合
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
(※相続放棄する本人と同じ名義なら不要)
- 収入印紙(800円分)
- 切手
- 相続人の親(被相続人の子)の死亡、または相続放棄を証明する書類
親の場合
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
(※相続放棄する本人と同じ名義なら不要)
- 収入印紙(800円分)
- 切手
- 被相続人の配偶者および子の死亡、または相続放棄を証明する戸籍謄本
祖父母、兄弟姉妹の場合
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
(※相続放棄する本人と同じ名義なら不要)
- 収入印紙(800円分)
- 切手
- 被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
- 被相続人の配偶者・祖父母・親・子の死亡、または相続放棄を証明する戸籍謄本
甥姪の場合
必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
(※相続放棄する本人と同じ名義なら不要)
- 収入印紙(800円分)
- 切手
- 相続人の親(被相続人の兄弟姉妹)の死亡または相続放棄を証明する戸籍謄本
- 被相続人の配偶者・祖父母・親・子・兄弟姉妹の死亡、または相続放棄を証明する戸籍謄本
上記の書類は、相続放棄の意思を証明し、相続人と被相続人の関係を明確にするためのものです。
相続放棄申述書は裁判所にてひな形が公開されているため、事前に用意しておくとよいでしょう。
相続放棄の手続き・申請の流れ

相続放棄を進める際には、以下の手順にそって進めましょう。
1 被相続人の財産調査を行う
2 必要書類を用意して家庭裁判所に提出する
3 家庭裁判所から照会書が届く
4 相続放棄申述受理通知書が届く
詳しく解説します。
1. 被相続人の財産調査を行う
相続放棄の決定前に、被相続人の財産全体を把握することが重要です。
財産調査により、財産の総額だけでなく負債が明らかになります。
たとえば、不動産や株といったプラスの資産と借金や債務を調査すれば、相続放棄をするかどうかの判断がしやすくなります。安易に負債を引き継がないように、細かい調査が不可欠です。
2. 必要書類を用意して家庭裁判所に提出する
相続放棄の手続きを進める場合、必要書類を揃えて家庭裁判所に提出します。
相続放棄の意向を正式に裁判所に伝えれば、法的手続きを開始できます。
提出する際には、書類に記入漏れや誤記がないか、最終確認を行いましょう。提出された書類は、裁判所による初期審査の対象となります。
3. 家庭裁判所から照会書が届く
提出した書類にもとづき、家庭裁判所から照会書が送付されてきます。
照会書によっては、提出書類に関する質問や追加情報の要求が含まれている場合があるため、迅速かつ的確に回答しましょう。
全ての要求に答えることで、手続きを次の段階へと進められます。
4. 相続放棄申述受理通知書が届く
最後に、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。通知書は相続放棄が法的に受理され、相続放棄の手続きが正式に完了したことを示した書類です。
通知書を受け取れば、財政的責任から免れることが確定し、相続放棄の手続きがすべて完了します。相続人は被相続人の財産だけでなく、負債からも法的に解放されます。
相続放棄の手続きを進める際の注意点

相続放棄を誤った方法で進めてしまうと、法的な問題や予期せぬ責任を負う可能性があります。手続きを進める際には、以下の点に注意しましょう。
- 相続放棄をしたら原則撤回できない
- 後順位の相続人に迷惑がかかる場合もある
- 相続人不在の際は相続財産清算人を選任する
それぞれ詳しく解説します。
相続放棄をしたら原則撤回できない
相続放棄を行った後の撤回は、原則として認められません。たとえば、相続人が相続放棄を申し立てを行って裁判所に受理された後は、被相続人の法定相続人ではなくなります。
相続財産に対するすべての権利を放棄したことになり、撤回ができなくなるのです。
相続放棄の決定は、遺産相続をしないという意思が明確であると裁判所に認められた場合にのみ成立します。
後順位の相続人に迷惑がかかる場合もある
相続放棄を行うことによって、他の相続人に迷惑がかかる恐れもあるため注意が必要です。たとえば、1人の相続人が借金を含む遺産の相続を放棄した場合、借金は自動的に他の相続人に割りあてられます。
結果、次の順位の相続人が負債を負担することになってしまいます。
相続放棄によって他の相続人に予期せぬ責任を強いる場合もあるため、全相続人と話し合いをしてから放棄するかを決めることが大切です。
相続人不在の際は相続財産清算人を選任する
相続人が一人もいない場合、裁判所は相続財産管理人を選任します。管理人の役割は残された財産を管理し、法的に適切な方法で分配することです。
管理人は法的な専門知識をもつ者が任命され、不動産の売却や銀行口座の清算を行ったりと、遺産を公平かつ効率的に処理します。
裁判所の監督のもとで行動し、すべての行動を記録し、関係者に報告しなくてはいけません。
まとめ|相続放棄に必要な書類は正しく準備しよう
相続放棄の手続きをスムーズに進めるためにも、必要書類を正確に準備することが大切です。相続人の立場によって必要書類は異なるため、手続き方法だけでなく用意すべき書類の内容を把握しておくことが大切です。
ただし、相続放棄の手続きは複雑で、漏れがあった場合は追加情報を要求されます。状況次第では時間がかかるケースも多いため、専門家のアドバイスのもと進めるのが得策です。
もし相続放棄についてお悩みであれば、「船橋・習志野台法律事務所」にご相談ください。
公式HP:船橋・習志野台法律事務所